
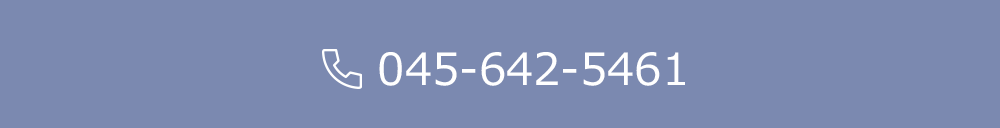

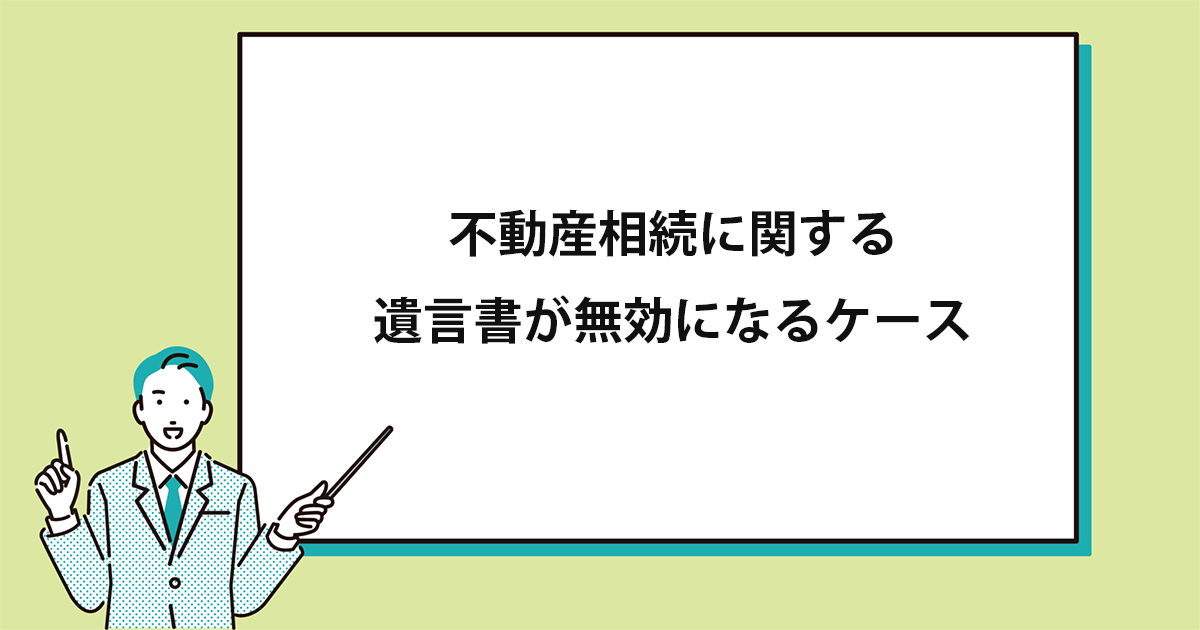
不動産を所有する方は、今後に備えて遺言書を用意しておくことが望ましいです。
これにより、相続させたい不動産の種類や人物などを明確にできます。
しかしこちらの遺言書は、不備があると効力が発揮されません。
今回は、不動産相続に関する自筆証書遺言が無効になるケースをいくつか解説します。
自筆証書遺言は、名前の通り被相続人が手書きで作成する遺言書です。
このことから、パソコンなどで作成したものは無効になります。
以前の法改正により、不動産等の詳細を記した目録部分は手書き以外でも作成できます。
そのため、パソコンで作成した財産目録を添付することは可能です。
その他、銀行通帳のコピーや登記事項証明書の添付も認められています。
ただし、法改正後でも目録以外の全文は手書きでなければいけません。
こちらのルールが混同している方は意外と多いため、注意してください。
不動産相続に関する自筆証書遺言を作成する場合、内容は明確にしなければいけません。
例えば“〇〇町の土地を〇〇に託す”と記載した遺言書があるとしましょう。
こちらの書き方は非常に曖昧です。
これだけでは土地を相続させたいのか、管理のみを任せたいのか判断できません。
“相続させる”という記載があれば、遺言書が無効になることもないでしょう。
また第三者でも特定できるよう、不動産の詳細も明確に記入しなければいけません。
“〇〇町の土地”ではなく地番や面積、地目などの情報も記しておきましょう。
不動産相続に関する遺言書には、必ず作成日の記入が必要です。
具体的には“令和〇年〇月〇日”など、年月日を特定できる書き方をします。
“令和〇年〇月吉日”という表現はNGです。
また自筆証書遺言の場合、被相続人の手書きで署名をしなければいけません。
遺言書は共同作成ができないため、必ず被相続人一人の名前のみ記入します。
さらに遺言書を無効にしないためには、捺印も必須です。
このとき使用する印鑑は、実印でなければいけないというルールはありません。
しかし偽造を防ぐためには、極力実印の使用をおすすめします。
ここまで、不動産相続に関する自筆証書遺言が無効になるケースを解説しました。
今回解説したケース以外でも、自筆証書遺言が無効になることはあります。
例えば加筆修正の手順が間違っている場合、共同で書かれている場合などです。
また遺言書には、公正証書遺言や秘密証書遺言もあります。
これらの遺言書が無効になることももちろんあるため、作成時は注意が必要です。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。
お問い合わせ

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F