
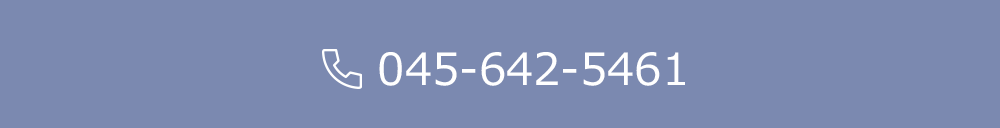

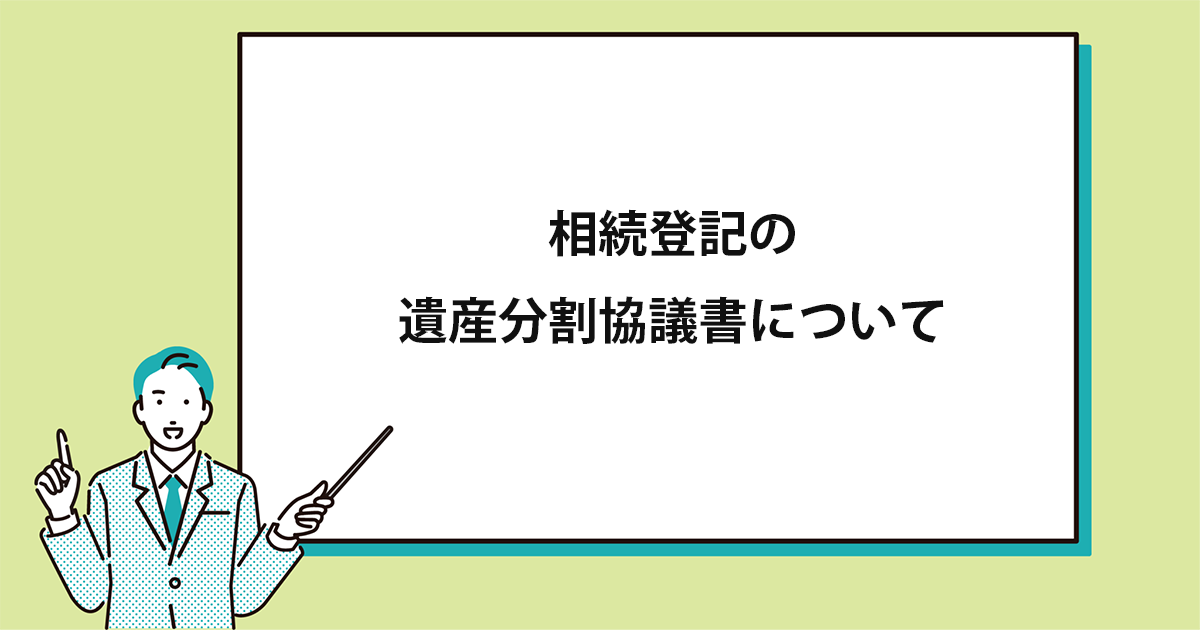
遺言書は不動産における被相続人が作成するものです。
これに対し遺産分割協議書は、不動産を引き継ぐ側の相続人が作成します。
また相続登記を行う際は、こちらの遺産分割協議書の提出が必要なケースがあります。
ここからは、相続登記の遺産分割協議書におけるポイントを解説します。
相続登記は、被相続人名義の不動産を相続人の名義に変更する手続きです。
こちらの手続きは、2024年4月1日から義務化される予定です。
手続きの期限については、相続で不動産を取得したことを知った日から3日以内です。
また被相続人の遺言書がない場合、相続登記では遺産分割協議書を提出します。
内容は不動産のみでも構わず、特にこれといった様式もありません。
ただし不動産の情報が正確に伝わらなければ登記申請はできません。
そのため所在や地目などについては、登記事項証明書通りに記入します。
相続人が相続登記に伴い遺産分割協議書を作成する場合、事前に行うことがあります。
具体的には相続人や相続財産の調査、相続人全員での遺産分割協議です。
遺産分割協議は相続人全員で行わなければいけません。
そのため最初に相続人の確定が必要になります。
こちらは、被相続人の本籍を管轄する役所で戸籍を調べて調査します。
また前述した通り、遺産分割協議書には不動産の細かな情報を記載する必要があります。
このことから、不動産の登記事項証明書の取得も必須です。
これらの準備がすべて終わった後、相続人全員で協議を行います。
そして協議で決定した内容をまとめ、遺産分割協議書を完成させます。
遺産分割協議書は自筆証書遺言とは違い、手書きで作成するというルールはありません。
そのため、パソコンで作成してもOKです。
紙のサイズや横書き・縦書きの定めもなく、記載事項以外は自由度が高いです。
相続人の氏名に関しても、パソコンで印字したもので問題ありません。
ちなみに相続人の中に高齢者の方がいる場合、代表者が氏名を印字しておきましょう。
こうすることで、後は高齢の相続人から捺印をもらうだけで済みます。
ここまで、相続登記に使用する遺産分割協議書のポイントを解説してきました。
相続登記の義務化に伴い、こちらの手続きは以前よりも重視されるようになりました。
しかし遺産分割協議書の作成は、場合によってはスムーズにいかないこともあります。
そのため今後不動産相続をする可能性がある方は、前もって知識を得ておきましょう。
また相続人同士の連絡についても、定期的に取っておくことが望ましいです。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。
お問い合わせ

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F