
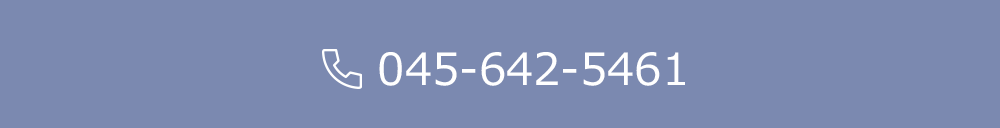

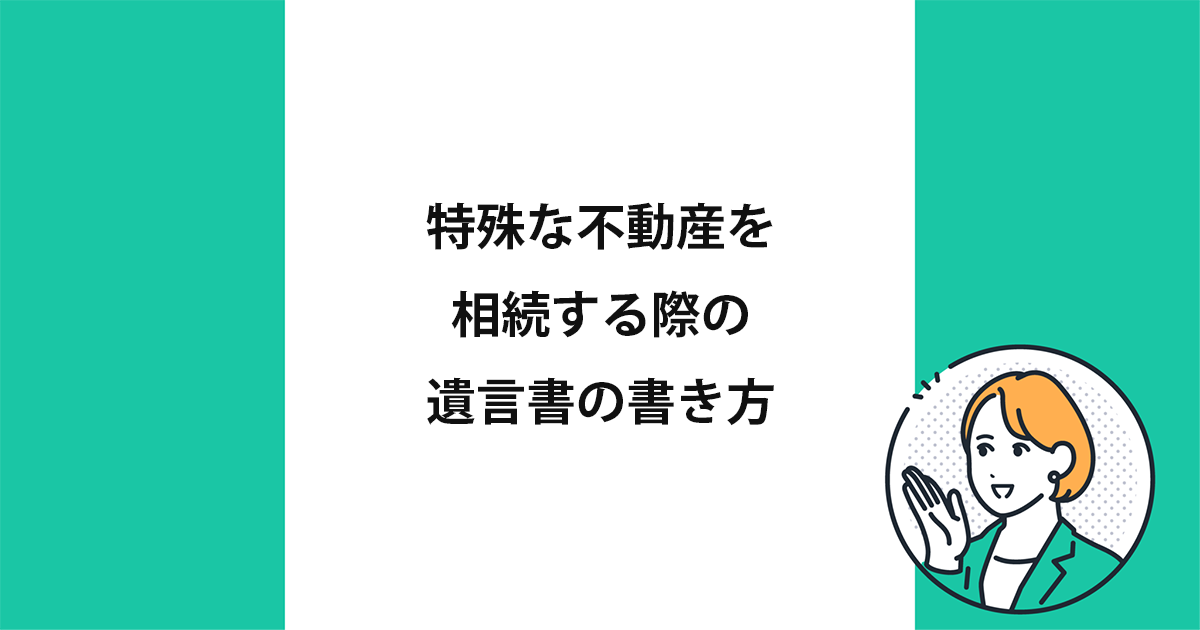
被相続人が亡くなると相続が発生しますが、このときの財産相続の仕方について記載されているのが遺言書です。
また、不動産を所有する被相続人は、物件の情報などを細かく記載しなければいけません。
このとき、特殊な不動産を相続する場合は、遺言書の書き方に注意が必要です。
今回は、書き方の例をいくつか紹介します。
アパートやマンションなどの収益物件を相続する場合、遺言書にはさまざまな契約関係について記載しなければいけません。
例えば、敷金返還債務や未収家賃請求権、火災保険特約などに関することです。
遺言書の条項の解釈により、これらの債権債務は、収益物件を相続した方が承継するとみるのが自然です。
しかし、包括条項(その余の財産・負債はAに相続させるなどの条項)と解釈関係を検討する必要が出てくることもあります。
そのため、できるだけ丁寧に記載した方が、相続人のためになります。
被相続人の中には、敷地権がない物件を相続しようとする方もいます。
例えば古いマンションの中には、敷地を使う権利と部屋の権利を一体化し、処分できるというルールができる前に建てられたものがあります。
このようなマンションは、2つの権利が一体化されていない可能性があります。
そのため、遺言書に情報を記載する際は、土地と建物を別々に特定しなければいけません。
土地については、所在や地番、地目や地積で特定します。
建物は一棟の建物の表示として家屋番号や建物の名称、種類や構造、床面積を記載します。
また専有部分の建物の表示として、同じ情報(家屋番号・名称・種類・構造・床面積)を再び記載します。
建物の付帯設備を相続する場合、遺言書には建物とは別に符号や種類、構造や床面積などを記載しなければいけません。
ここでいう付帯設備とは、建物の敷地内にある倉庫などが該当します。
付帯設備に関する記載がないと、相続の際に「誰が相続するのか?」というトラブルが発生する可能性があります。
そのため、たとえ金銭的な価値がないものであっても、相続する人物や方法などについては記載しておきましょう。
遺言書は、不動産をはじめとする相続財産の取り扱いについて、相続人の負担を軽減するためには必要なものです。
しかし内容が不十分だと、かえって相続人の負担を大きくしてしまったり、困惑させてしまったりすることになります。
そのため、被相続人はじっくり時間をかけて遺言書を作成し、内容に不備がないかどうかを確認しておかなければいけません。
お問い合わせ

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F