
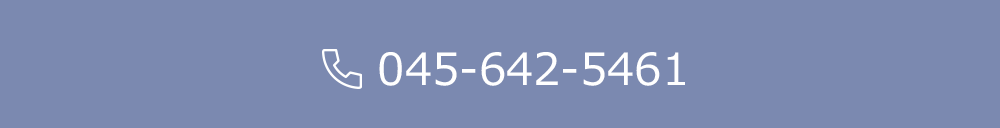

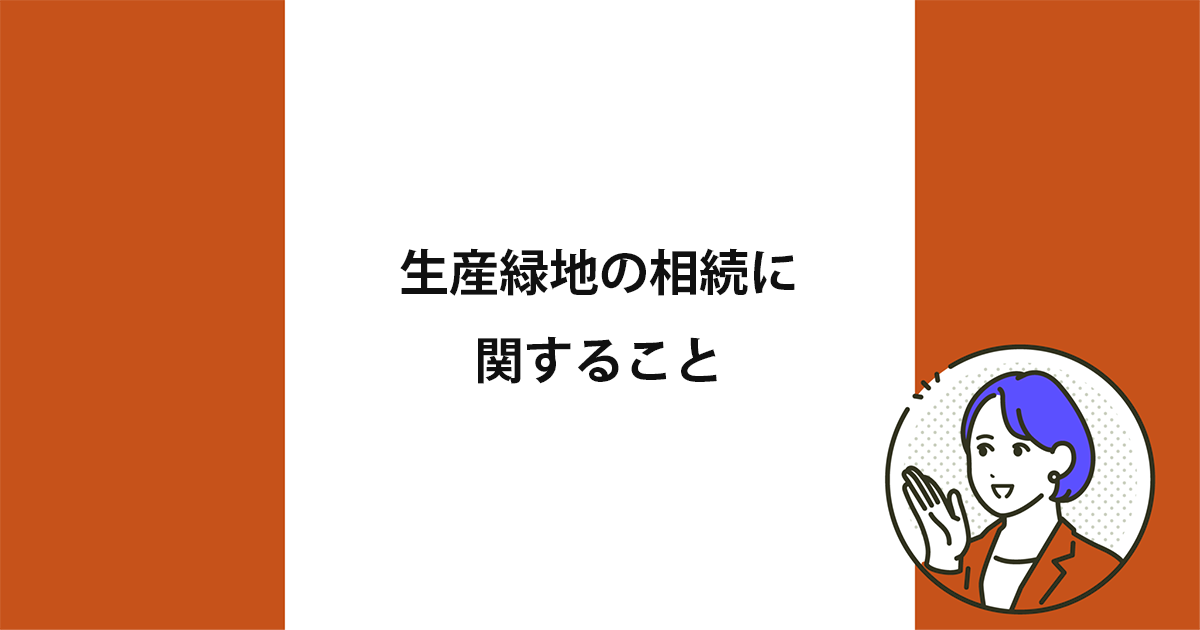
良好な都市環境の形成を図るため、市街化区域内農地の緑地としての機能を活かし、計画的に保全されるのが生産緑地です。
また、被相続人が生産緑地を所有していた場合、相続人の方は生産緑地を引き継ぐことになります。
今回は、生産緑地の相続に関することをいくつか解説します。
生産緑地を相続した方は、その扱いについて以下の3つから選択できます。
| ・指定の継続 ・指定の解除 ・指定の一部解除 |
生産緑地の指定を継続すれば、固定資産税や相続税等の優遇を受けられますが、生産緑地法による行為制限などの義務が課されます。
一方指定を解除すれば、生産緑地法による制限もなくなりますが、税負担は重くなります。
ちなみに、市町村によっては、一部の解除のみ認めているところもあります。
なお一部解除の場合、残った生産緑地には相続税の増税猶予が継続して適用されます。
しかし、そのためには指定解除する範囲について、猶予適用農地等全体の20%以下に収めなければいけません。
生産緑地の相続税評価額は、以下のように計算します。
| ・その土地が生産緑地でないものとして評価した価額×(1-AまたはBの割合) |
課税時点で買取り申出ができない生産緑地の場合、買取り申出ができるようになるまでの残りの期間に応じ、以下の割合を適用して上記のAとします。
| 期間 | 割合 |
| 5年以下 | 10% |
| 5~10年 | 15% |
| 10~15年 | 20% |
| 15~20年 | 25% |
| 20~25年 | 30% |
| 25~30年 | 35% |
課税時点ですでに買取り申出が行われていた、もしくは行える生産緑地の場合は、5%を適用して上記のBとします。
なお具体的な評価額を算出するには、さらに複雑な計算が必要になるため、詳しくは専門家に相談することをおすすめします。
生産緑地にかかる相続税については、相続人の就寝営農を条件に、納税や猶予される制度があります。
こちらの猶予を適用するためには、以下の書類を相続税の申告書とともに提出しなければいけません。
| 書類 | 取得方法 |
| 相続税納税猶予の特例適用の農地等該当証明書 | 市町村の都市計画課にて取得 |
| 相続税納税猶予に関する適格者証明書 | 市町村の農業委員会にて取得 |
ちなみに、これらの書類は、相続税の申告期間10ヶ月間で揃えなければいけません。
生産緑地は特殊な土地であり、通常の不動産のようにスムーズに相続できないことがあります。
相続に伴う選択や手続きも多く、事前にある程度特徴を掴んでおかなければ、相続が長期化する可能性も高いです。
さらに、相続後も増税猶予を継続する場合は、適宜手続きを行う必要があります。
そのため、税理士などの専門家における力が欠かせません。
お問い合わせ

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F