
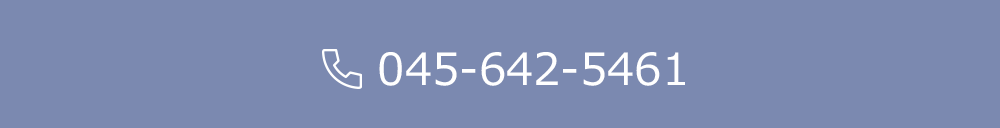

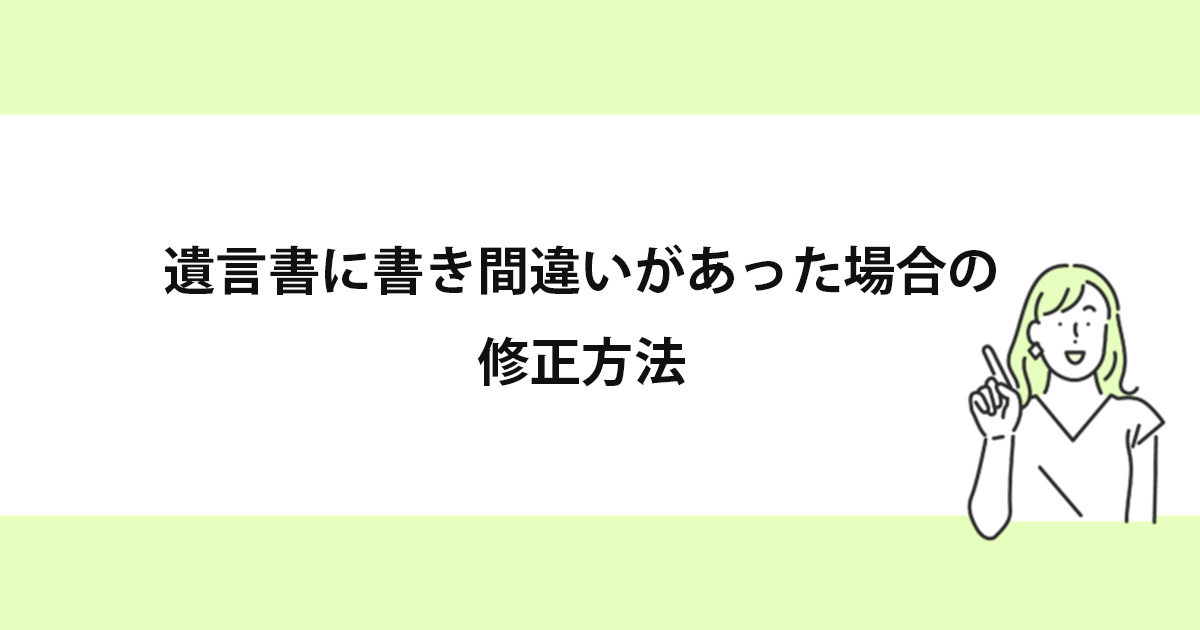
自身が所有する預貯金や不動産などについて、自身の思惑通り相続したいと考える方は、遺言書を作成します。
また遺言書の多くは、被相続人本人が作成する自筆証書遺言です。
ではこちらの内容に書き間違いがあった場合、どのように修正すれば良いのでしょうか?
今回は正しい修正方法を中心に解説します。
自筆証書遺言を作成している段階で書き間違いが発生した場合、まずは訂正する文字を二重線で消し、訂正後の文字を記入します。
その後、訂正した箇所に印鑑で押印します。
このとき使用するのは、遺言書におけるその他の部分で使用したものと同じ印鑑です。
訂正した文字が見えるように押印するのがポイントです。
また加筆箇所の欄外もしくは遺言書に末尾に、“〇字削除”、“〇字加入”と記載し、その下に被相続人が署名を行います。
ここまで行って初めて、書き間違いが修正されたことが認められます。
自筆証書遺言で書き間違えた部分を修正するのではなく、完全に削除したい場合もあるかと思います。
このようなケースでは、削除したい部分に二重線を引き、その近くに訂正印を押します。
そして削除した箇所の近く、あるいは遺言書の末尾に削除した内容を書き、被相続人が署名します。
例えば、遺言書の4行目の文章をすべて削除したいとします。
この場合、“4行目の第2条全文を削除した ○○○○(被相続人の氏名)”といったように記載すれば、一部の内容の削除が認められます。
上記のようなルールに従わず、遺言書を修正してしまうケースは、自筆証書遺言では十分起こり得ることです。
例えば線で消しただけで押印がない場合などは、修正が認められないことになっています。
そのため、書き間違いがあるままの遺言書として法的に有効なものになってしまいます。
遺言書自体が無効になるのではなく、修正が無効になるというのがポイントです。
ちなみに、修正方法がルールに従っていない場合でも、明らかな誤記と判断される場合は遺言書の効力に影響がないという判例もあります。
テンプレートをダウンロードしたり、書き方をネットなどで調べたりすれば、被相続人一人でも自筆証書遺言を作成することは可能です。
しかし遺言書を作成するのは基本的に人生で1回であり、細心の注意を払っていても、記入や修正に関するミスが起こる可能性は高いです。
そのため、被相続人の方はトラブルを防ぐためにも、弁護者や行政書士、税理士などの専門家のサポートを受けることをおすすめします。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。
お問い合わせ

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F