
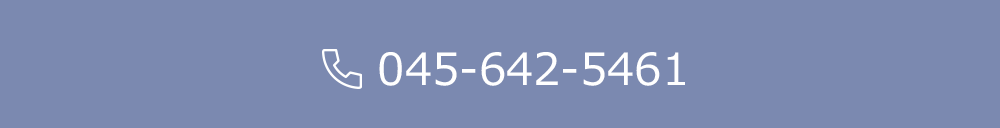

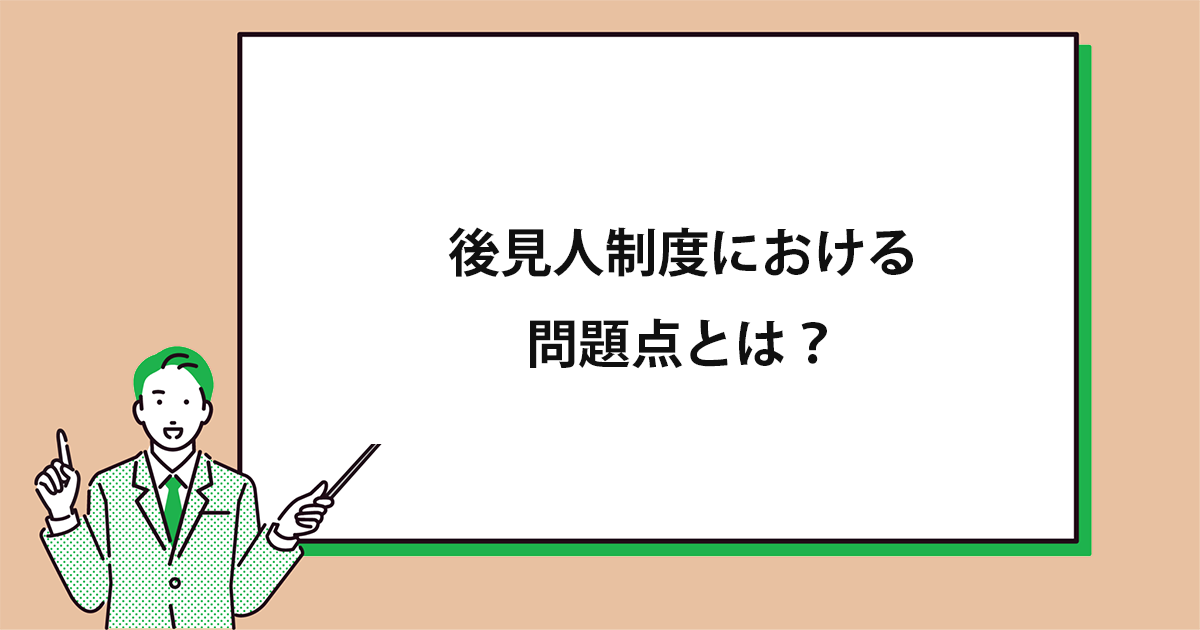
後見人制度は、判断能力が低下した方の生活、預貯金や不動産などの財産を保護するための精度です。
被後見人が悪徳商法や詐欺などの被害に遭うことや、家族間の紛争を防止できるメリットがある反面、利用にあたっては問題点もあります。
今回は、こちらの問題点について解説します。
後見人制度を利用する際は、ある程度の費用と手間がかかります。
そのため、誰でも気軽に利用できるというわけではありません。
費用については申立手数料が1万円程度、戸籍謄本や住民票の取得費用が数千円程度、医師の診断書や鑑定費用がそれぞれ数万円程度かかります。
また専門家に依頼する場合、他にも着手金や報酬などが発生します。
弁護士や司法書士に依頼した場合、それだけで30~50万円程度の費用が発生することも珍しくありません。
さらに申立から後見開始までには通常3ヶ月前後かかり、急を要する場合は対処が難しいです。
後見人制度では、被相続人の不動産などの財産について、変更や活用が認められていません。
許可されているのはあくまで保護のみです。
そのため、例えば被相続人が複数の不動産を所有している場合でも、それを賃貸物件として経営することなどはできません。
また相続税対策として被相続人の預貯金で不動産を購入したり、保険に加入したりすることもできないため、注意が必要です。
さらに後見人が被後見人と同居している場合、生活費の負担割合を明確にしなければならず、こちらは非常に煩雑になることがあります。
被後見人の財産を保護するのが後見人制度であるため、後見人は当然その家族や親族が務めると思いがちですが、実際はそうとは限りません。
近年は、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることも多くなっています。
最高裁判所事務総務局家庭局のデータによると、2000年には後見人の91%を親族が務めていたにもかかわらず、2022年はわずか19%にまで減少しています。
また専門家が後見人に選ばれた場合、家族や親族の意向と財産保護に関する意向が合わないおそれがありますし、報酬も支払わなければいけません。
後見人制度は便利であるものの、安易に利用しない方が良いという声が多いのも事実です。
それは、前述したようなさまざまな問題点や課題があるからです。
しかし、あらかじめ注意点を知った上で利用するのであれば、何の問題もありません。
被後見人にとっても、後見人にとっても希望通りの制度となるように、慎重に手続きを進めていきましょう。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。
お問い合わせ

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F