
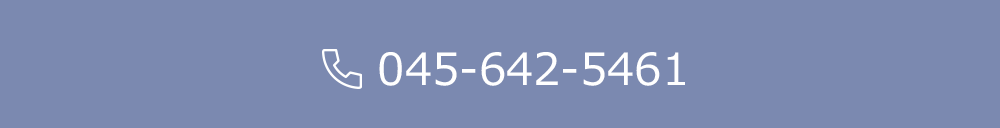

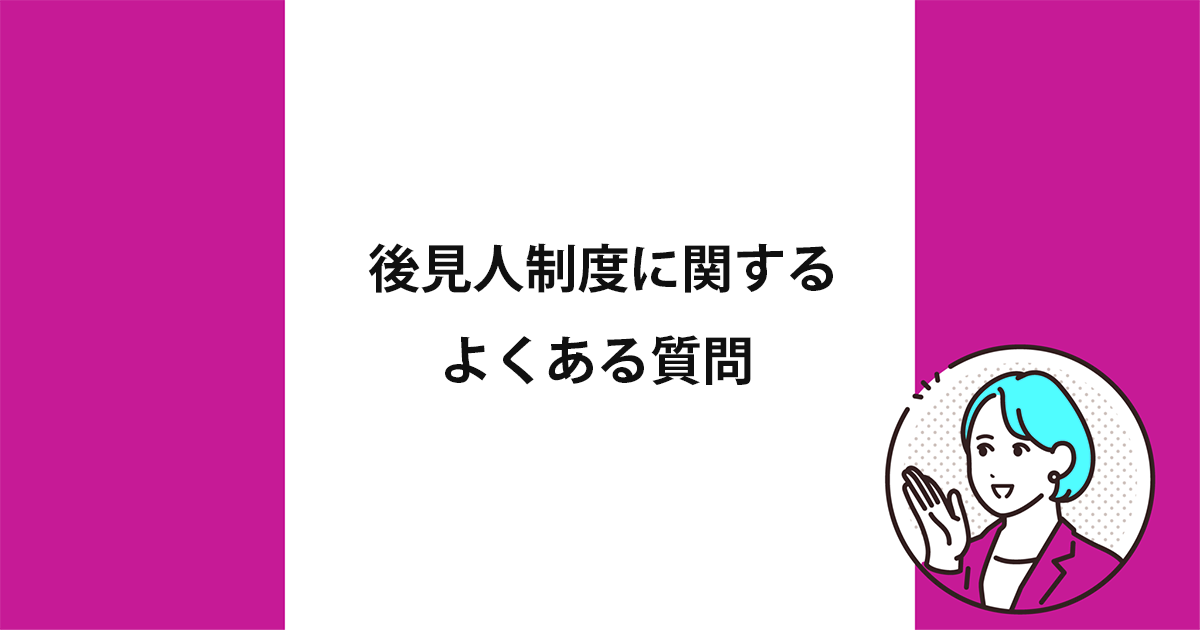
後見人制度は、超高齢化社会が進む日本において、年々重要性が増してきている制度です。
2025年には、認知症患者が730万人を超えると推計されているため、その方々の支援を行う受け皿として期待されています。
今回は、そんな後見人制度に関するよくある質問にお答えします。
例えば高齢の方であっても、必ずしも認知機能が衰えているとは限りません。
しかし、頭がしっかりしていても、身体が衰えて財産管理の負担が大きくなっている方は多いです。
またこのような状態の方でも後見人制度は利用できるのかというと、残念ながら利用できません。
後見人制度は、あくまで判断能力が不十分な方をサポートする制度です。
もし、身体が不自由なことが理由でサポートを必要としているのであれば、専門家と財産管理委任契約を結ぶことが望ましいです。
後見人側の意見として多いのは、「後見人を務めるにあたって資格はいるのか?」という疑問です。
後見人には、国家資格や公的資格、その他の認定資格も一切不要です。
求められるのは、後見人としてふさわしい属性であることです。
現実問題として、以下のような方は後見人としてふさわしくないと判断されます。
・すでに相当の高齢に達している
・病気がち
・被後見人との間に金銭の貸し借りがある
・いざというときすぐに被後見人に元に来られない など
また法定後見の場合、家庭裁判所が適当でないと判断すれば、親族などが後見人として認められないこともあります。
後見人制度における後見人の役割の一つに、被後見人の財産管理が挙げられます。
こちらは預金通帳や印鑑の管理、公共料金や税金の支払い、不動産の管理や処分などが含まれます。
また被後見人が不利益な契約を結んでしまった場合には、取消権を行使できます。
一方贈与や投資など、積極的な財産運用管理については、後見人には認められていない行為です。
さらに、本来は親族が支払うべき費用や支払いなど、被後見人本人の利益にならない支出も、財産管理の範囲からは外れています。
ファミリー世帯では、早めに両親の判断能力が衰えた場合に備えて、後見人制度について理解しておかなければいけません。
ここでファミリー世帯という言い方をしたのは、被後見人となる方だけでなく、その後見人になり得る子どもなどの家族も理解すべき制度だからです。
また後見人制度だけでなく、家族信託など別の方法で両親の財産を守ることも検討しなければいけません。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。
お問い合わせ

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F