
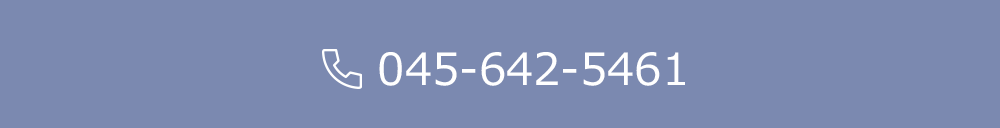

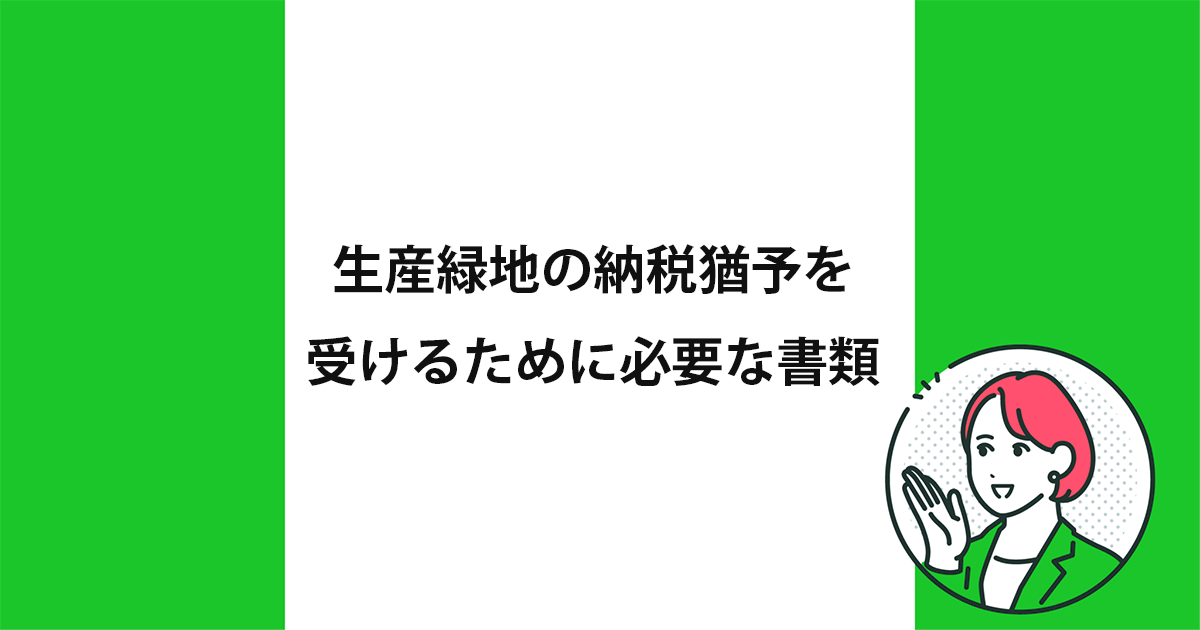
生産緑地を相続によって取得した場合、一定の要件をクリアすれば、農業投資価格による価額を超える部分に対応する相続税が猶予されます。
こちらがいわゆる、生産緑地の納税猶予です。
今回は、生産緑地を相続した方が納税猶予を受けるために、提出しなければいけない書類について解説します。
適格者証明書は、生産緑地を相続した方が、納税猶予を受ける場合の相続人の適格要件に該当することを証明する書類です。
こちらを取得する際の流れとしては、まず相続した生産緑地がある地域の農業員会に対し、適格者証明願を提出します。
適格者証明願は、被相続人が死亡の日まで農業を営んでいたこと、農業相続人が農業経営を継続することを証明する書類です。
適格者証明願が承諾された場合は、適格者証明書が発行されるため、こちらを税務署に提出します。
担保提供書は、適格者証明書とあわせて税務署に提出する書類です。
具体的には、納税猶予を受ける際、その担保として提供する不動産を明確にするために必要なものです。
ここでいう不動産には、当然相続した生産緑地が該当します。
また担保提供書には、提供する担保の種類や所有者、評価額といった情報が記載されています。
さらに、担保の登記事項証明書、明細書などの書類を添付することもあります。
抵当権設定登記申請書は、不動産に抵当権を設定することについて、登記簿に記録するための書類です。
こちらの申請書には、金融機関などの抵当権者、抵当権設定者、抵当権設定の対象となる不動産の情報、債権額などが記載されます。
一般的に、こちらの書類は住宅ローンなどを利用する際法務局に提出するものですが、生産緑地の納税猶予を受ける場合は税務署が提出先になります。
ちなみに前述した3種類の書類を提出し、生産緑地の納税猶予の承諾を得れば、申請が終了するというわけではありません。
納税猶予を継続するためには、3年後ごとに継続届出書を税務署に提出する必要があります。
なぜなら途中で農業が継続できなくなった場合、生産緑地の指定は解除され、納税猶予も終了するからです。
急に生産緑地を相続することになった場合、通常の不動産とまったく特徴が異なることから、手続きの際にバタバタしてしまうことも多いかと思います。
また相続税については、被相続人が適切な準備をしていなかった場合、相続人にとって大きな負担になり得ます。
そのため、農業を営む家計において相続人になり得る方は、前もって生産緑地の納税猶予について知っておくべきです。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。
お問い合わせ

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F