
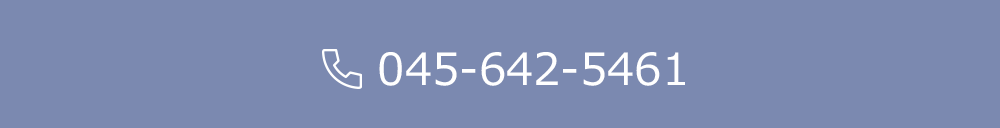

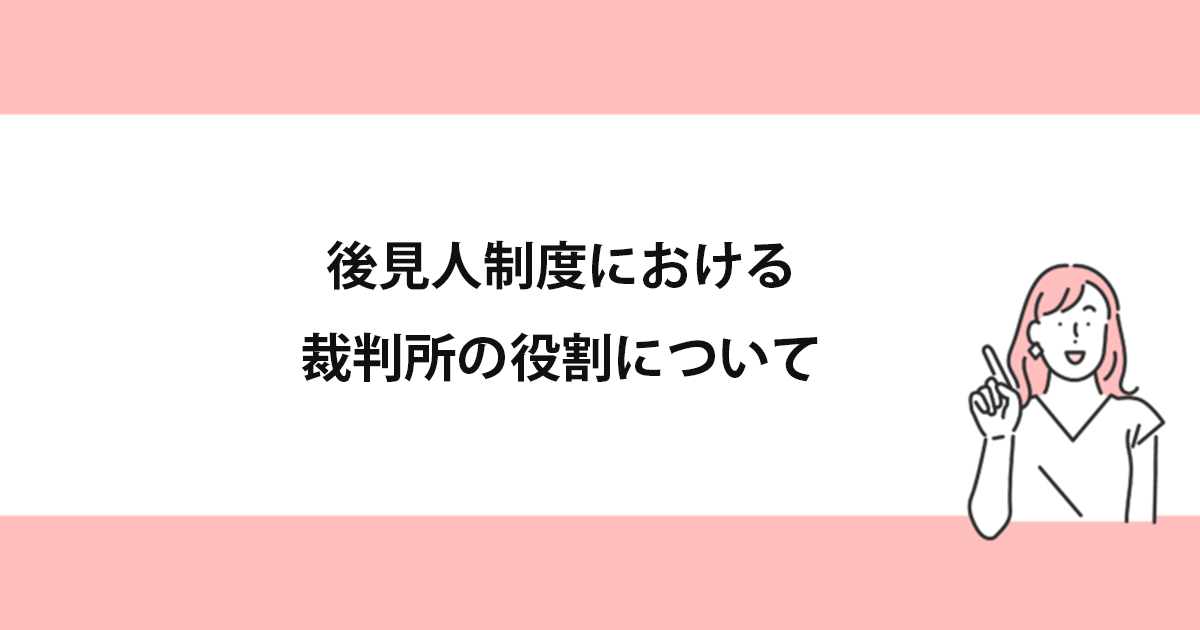
今後後見人制度を利用する予定がある方は、制度の概要について、なるべく多くの知識を持っておくことが望ましいです。
また後見人制度と深い関係があるのが、国民の権利と自由を守る国家機関である裁判所です。
今回は、後見人制度における裁判所の主な役割について解説します。
家庭裁判所は認知症や知的障害などの理由により、判断能力が不十分になった本人、その家族などから申し立てを受け、後見人等を選任します。
ここでいう後見人等には、成年後見人や保佐人、補助人などが含まれています。
成年後見人は判断能力を常に欠く被後見人が対象であり、その本人の財産は包括的に管理されます。
保佐人については、著しく判断能力が不十分な方の特定の法律行為を代理・同意でき、補助人は家庭裁判所が定めた特定の法律行為の代理・同意を行います。
つまり権限については、後見人>保佐人>補助人の順に強くなるということです。
家庭裁判所における後見人等選任の決定については、不服を申し立てることができません。
裁判所は、選任された後見人や保佐人、補助人における職務を監督する役割も担っています。
選任された後見人等は、定期的に家庭裁判所に対し事務の状況を報告しなければいけません。
このとき、家庭裁判所は適切な職務が行われているかどうかを監督し、不適切な点があれば指導します。
また財産の私物化など、不正行為が疑われる場合、家庭裁判所は後見監督人を選任し、後見人の事務をチェックすることもあります。
裁判所は、単純に後見人制度の申立先としても機能する機関です。
後見人制度を利用するための申立は、被後見人本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
このとき、申立には収入印紙代などの費用がかかります。
また申立が行われたからといって、すぐに後見人等の選任がスタートするわけではありません。
申立後は、被後見人となる本人の判断能力を調べるために、医師による鑑定が行われる場合があります。
これによって制度を利用することに問題がないと判断された場合、裁判所は後見人等の選任に移ります。
後見人制度と裁判所は、切っても切れない関係にあります。
申立を行うのも裁判所ですし、その申立内容を精査して後見人等の選任を行い、後見人等監督を行うのも裁判所です。
そのため、今後後見人制度を利用する際は、管轄となる裁判所についてある程度の情報を集めておくべきです。
もちろん、その他の後見人制度の知識についても、できる限り集めておくことを心掛けましょう。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。
お問い合わせ

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F