
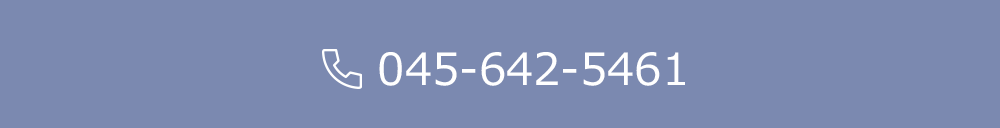

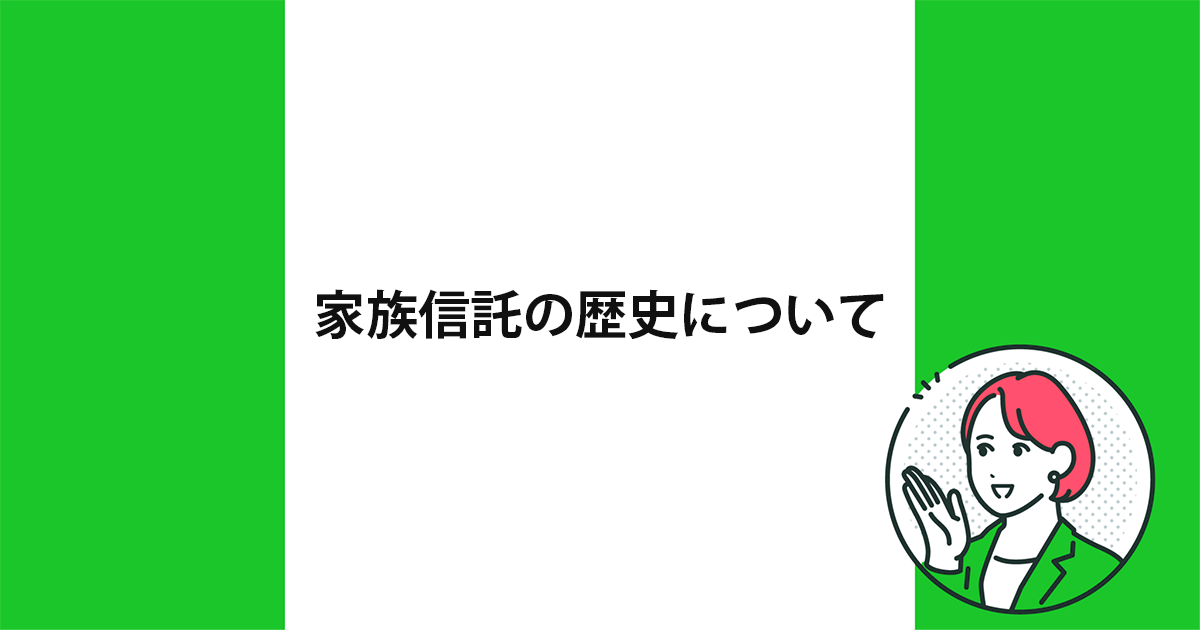
財産を所有する委託者が、その財産を家族である受託者に託し、あらかじめ定めた目的にしたがって管理・処分してもらう制度が家族信託です。
近年は認知症や高齢化対策として利用する方も増えている当制度ですが、こちらには一体どのような歴史があるのでしょうか?
今回は、家族信託の歴史について解説します。
家族信託は、2007年の信託法改正によって広く知られるようになりましたが、その根底にある信託という概念は遥か昔から存在していました。
信託の起源は、中世ヨーロッパにまでさかのぼります。
十字軍の兵士たちは、長期の遠征に出る際、もしものことがあっても家族が困らないように、信頼できる友人に土地や家屋などの財産の管理を託しました。
また当時は法律によって財産の移動が厳しく制限されていたため、財産の所有権(名義)とそこから得られる利益を受け取る権利を分離する“ユース”という仕組みが発展しました。
この慣習は、その後イギリスの裁判所で法的な保護を受けるようになり、現代の信託制度の原型が確立されていったとされています。
日本に信託の概念が導入されたのは、明治時代後半~大正時代前半です。
また1922年には、旧信託法と旧信託業法が制定されました。
この時代には、営利目的の信託会社の規制を主眼としていて、個人が利用する仕組みとして信託はほとんど普及していませんでした。
また戦後、経済復興の資金供給源として、信託銀行による貸付信託などの商事信託が発展しています。
この時期も、信託はまだ一般の家庭にとって馴染みのないものでした。
日本の家族信託が本格的に普及するきっかけとなったのは、2000年代の信託法改正です。
高齢化社会の進展とともに、高齢者の財産管理や遺産継承を目的とした信託への期待が高まりました。
そして84年ぶりに信託法が抜本的に改正され、2007年に施行されました。
これにより、信託銀行などの信託業者だけでなく、家族などの個人でも受託者になれる民事信託の仕組みが利用しやすくなっています。
この民事信託こそ、現在多くの方に利用されている家族信託とほぼ同じものです。
現在利用されている家族信託は、紆余曲折あって適切な形に行きついたという歴史があります。
そのため、認知症対策や円滑な相続税対策の一環として、家族信託は利用を検討すべき制度の一つだと言えます。
もちろんすべての方に向いているわけではありませんが、財産を持つ方とその家族は、今後について話し合いをする際、家族信託についても意見を交わすことをおすすめします。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。
お問い合わせ

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F