
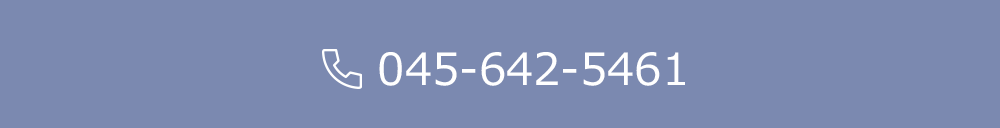

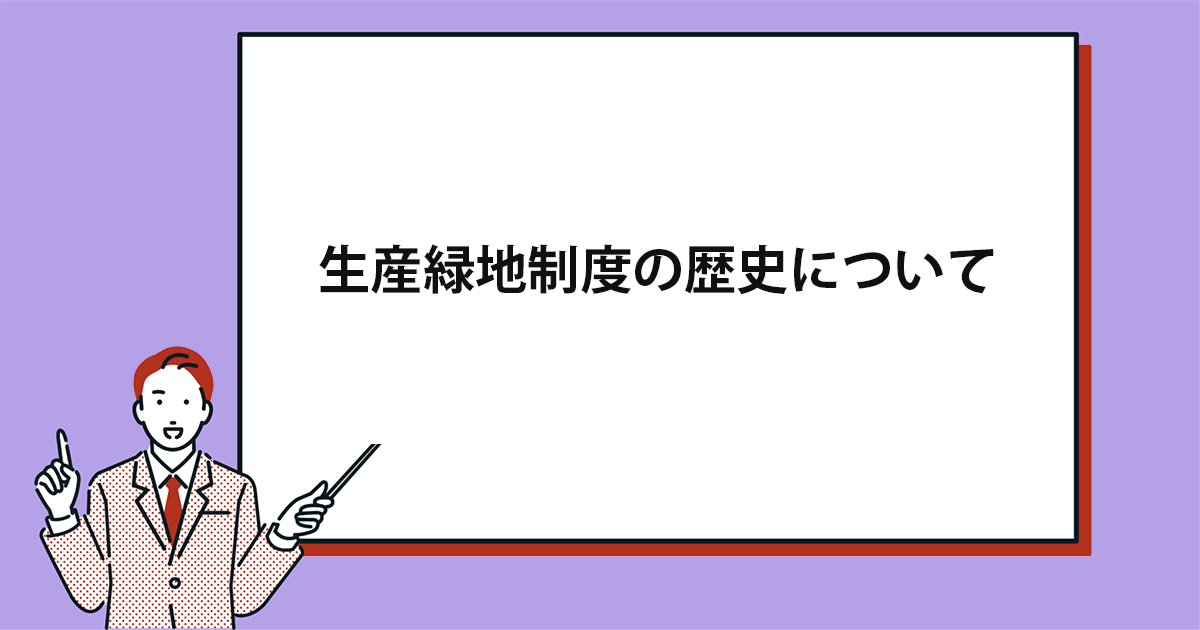
生産緑地を所有する方は、それを売却する際に指定解除を行わなければいけません。
つまり、制度に従って売却を進めていかなければいけないということです。
では、生産緑地制度は、いつどのように始まった制度なのでしょうか?
今回は、生産緑地制度の制定や変遷などについて解説します。
生産緑地制度は、1974年に制定されました。
日本では高度経済成長期、宅地不足が深刻化しました。
このことを受け政府は、市街化区域内の農地の宅地転用を促すため、税制上の措置を講じます。
しかし、急速な宅地化は都市環境の悪化や災害リスクの増大につながるとして問題視され、無秩序な開発を抑制する目的で生産緑地制度が制定されています。
都市の良好な環境を維持しつつ、市街化区域内の農地を計画的に保全することを目指す制度として、注目を集めました。
生産緑地制度は、1992年に大きな改正が行われています。
当時はバブル経済期の地価高騰を受け、都市農地の宅地化を促進することと、税負担の公平性を確保することが強く求められました。
また1974年当初の制度では、生産緑地がほとんど指定されず、制度の形骸化が進んでいきました。
このような状況を受け、生産緑地制度は宅地化すべき農地と保全すべき農地を明確に区分し、都市農地の計画的な保全をより強めるために改正されました。
具体的には生産緑地における30年間の営農義務や指定基準の緩和、税制優遇の継続などが盛り込まれています。
生産緑地制度は大きく改正されましたが、後に2度目の大改正を迎えます。
こちらは、2022年問題への対応が喫緊の課題になったからです。
2022年問題は、前述の改正で指定された多くの生産緑地が、30年の期間が満了する2022年に一斉に指定解除され、市場に出回ることで地価が下落するという問題です。
こちらに対応すべく、2017年に政府では特定生産緑地制度や要件の緩和、行動制限の緩和などの改正が行われました。
特定生産緑地制度は、所有者が希望すれば買取申出期間を10年間延長できるという制度です。
また生産緑地の面積要件は500㎡から300㎡に引き下げられ、直売所やレストランといった施設の設置も可能になっています。
生産緑地制度はお世辞にもシンプルな制度とは言えませんが、現行の形にたどり着くまでにはさまざまな紆余曲折がありました。
もちろん、現行の制度がまったく隙のない完璧なものであるかどうかはわかりませんが、少なくとも制定当初よりは利用しやすいものになっています。
そのため、生産緑地を所有する方やその相続人になり得る方は、少しでも生産緑地制度のことを知っておきましょう。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。
お問い合わせ

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F