
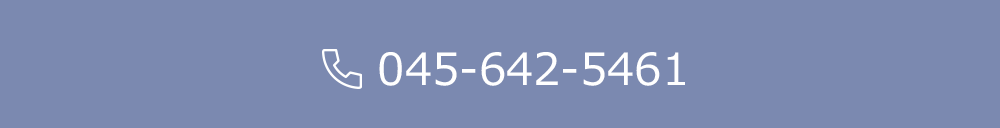

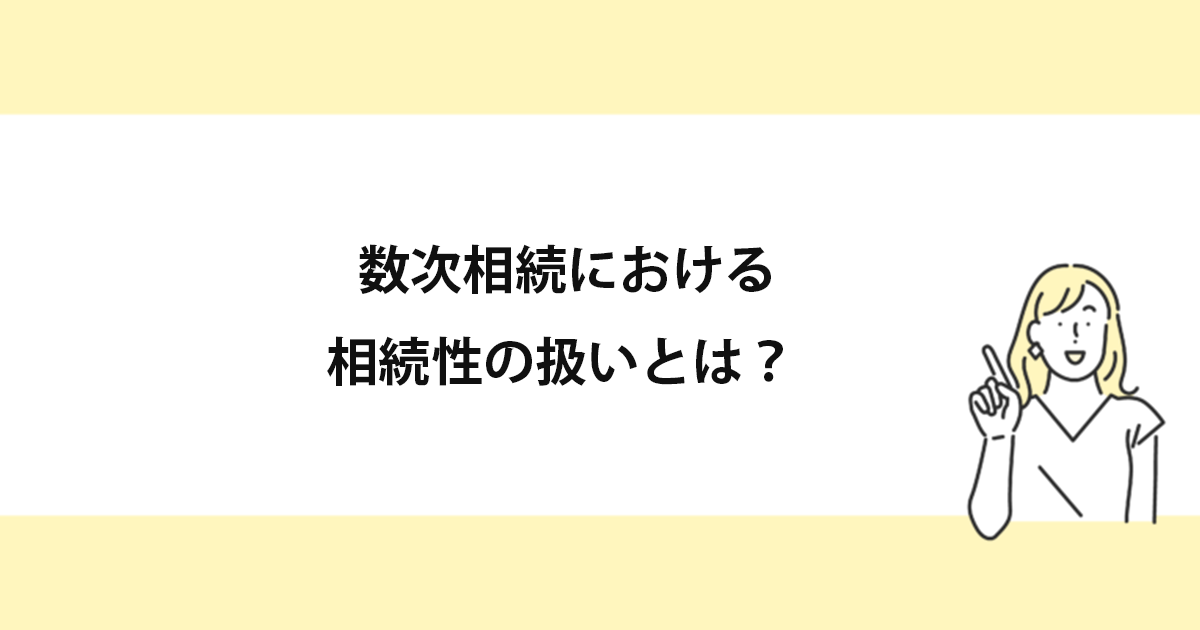
相続と言えば、一般的なのは被相続人が亡くなったとき、その相続人に預貯金や不動産などの財産が相続されるケースです。
こちらは一時相続とも呼ばれますが、特殊なケースに数次相続というものがあります。
今回は数次相続の概要と、数次相続における相続税の扱いについて解説します。
数字相続は、被相続人が亡くなった後、遺産分割を完了させる前に相続人が亡くなり、次の相続が発生するというものです。
冒頭で触れたように、一般的な相続には被相続人とその相続人が関与します。
しかし、相続人が亡くなった場合、一般的な相続を行うことはできません。
例えば父が亡くなったケースで、母と子どもがいる場合、相続人は母と子どもの2人になります。
しかし、遺産分割協議がまとまらないうちに母が亡くなった場合、二次相続人となった子どもが父と母の相続手続きをあわせて行うことになります。
一時相続の相続人が亡くなった場合、その人が行うべきだった一時相続の相続税の申告と納税義務については、二次相続の相続人が引き継ぎます。
つまり二次相続人は、一時相続と二次相続の相続税を申告・納付しなければいけないということです。
また相続税の申告期限は、相続発生を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
しかし一時相続の申告期限が来る前に一時相続人がなくなった場合、その一時相続人の相続分に関する申告期限は、二次相続が発生した日から10ヶ月後まで延長されます。
ただし、期間が延長されるのは、二次相続人に引き継がれた部分のみです。
一時相続の存命の相続人の申告期限は延長されないため、全員の申告期限が異なる場合があります。
数字相続では、同じ財産に短期間で相続税が二重に課税されることがあります。
この重複した負担を軽減するために、相次相続控除という制度が設けられています。
こちらの適用要件は、前の相続から今回の相続までの期間が10年以内である場合のみです。
また控除額については、一時相続で課税された相続税額のうち、一定額を二次相続の相続税額から控除できます。
控除額は、前の相続から経過した期間に応じ、1年につき10%減額されます。
数次相続は非常に稀なケースですが、誰しも起こり得ることだとも言えます。
特に両親が両方高齢で、なおかつ体調を崩している場合などは、遺産分割協議が終わるまでに相続人である父や母が亡くなることは十分考えられます。
また相続税の扱いについても少し複雑になるため、今後相続をする可能性がある方は念頭に置いておきましょう。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取していま
お問い合わせ

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F