
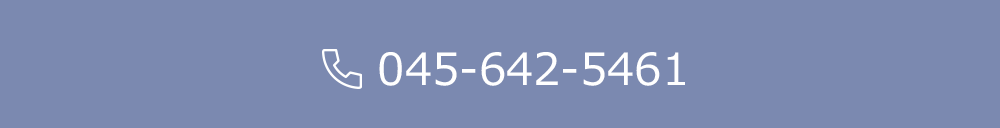

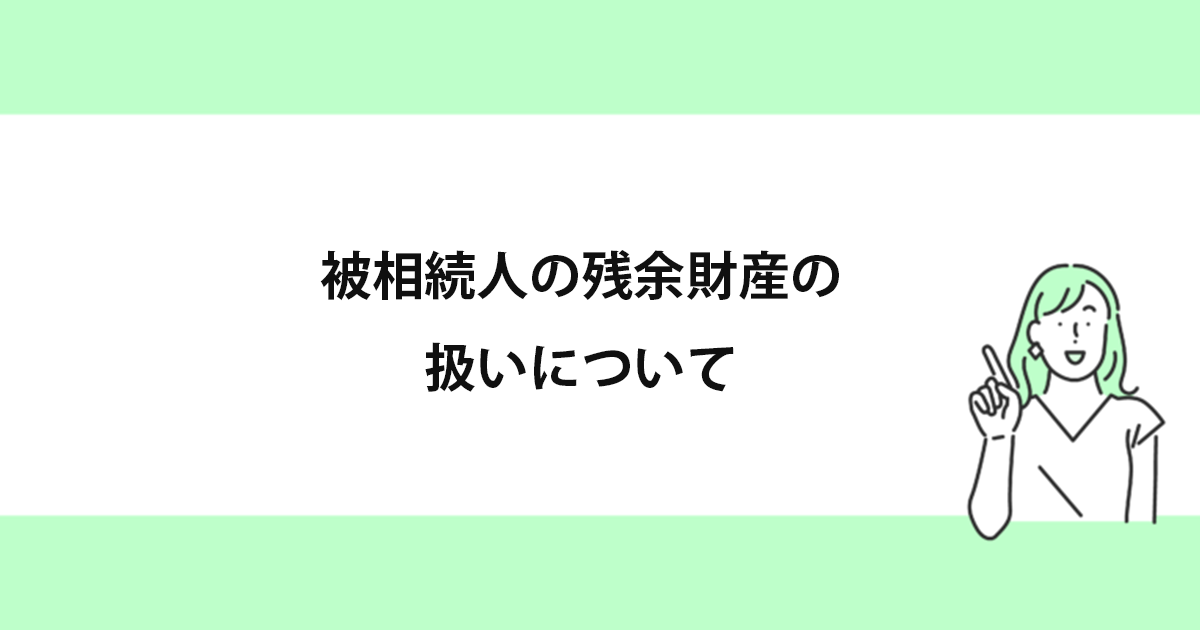
相続におけるもっとシンプルな形は、被相続人が遺した遺言書の内容に沿って、相続人がそれぞれ財産を受け取るというものです。
しかし、被相続人に残余財産が存在する場合、相続は少し複雑になります。
今回は残余財産における概要と、こちらが存在する場合の相続における取り扱いについて解説します。
残余財産は、遺言書に相続先が記載されていない財産です。
例えば遺言書の中に、「不動産〇〇はAに相続する」という記載がある場合、その不動産は当然相続人Aが引き継ぐことになります。
しかし被相続人が他にも不動産を持っているにもかかわらず、こちらは誰に相続させるのかを記載していないとします。
この場合、相続人が明確になっていない不動産は残余財産という扱いになります。
遺言書にその承継先や処分方法などが記載されていない残余財産については、どのように扱うかを遺産分割協議で決定します。
具体的には、相続人全員で集まって話し合い、誰が取得するのかを決めることになります。
また遺産分割協議がまとまらない場合や、協議を行わない場合は、民法で定められた法定相続分に従って財産を承継します。
法定相続分は、相続人の構成によって割合が異なります。
被相続人における残余財産は、いわば遺言書への記載漏れです。
そのため、トラブルを避けるために、被相続人はすべての財産について具体的な内容を記載しておかなければいけません。
例えば、預貯金や不動産を含むすべての財産を特定の人物に相続させる場合、「遺言書は所有するすべての財産を妻である○○に相続させる」などと記載します。
このとき“すべての財産”と記載するのがポイントで、この記載方法にすることにより、残余財産は一切発生しなくなります。
また特定の財産以外を包括的に遺贈する場合は、「上記以外の遺産のすべてを長男○○に包括して遺贈する」などと記載するのがポイントです。
もちろん、複数の相続人に細かく相続する財産を分けても構いませんが、そうするときも残余財産が発生しないようにチェックしなければいけません。
被相続人が想像している以上に、遺言書は相続において強い力を持ち、相続人の人生を左右するものです。
そのため、自筆証書遺言の場合は、内容が適切であるかどうか細かく確認しながら、慎重に作成しなければいけません。
また相続の内容については、相続人同士のトラブルにつながらないよう、できる限りすべての相続人にとって平等なものにすることが望ましいです。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。
お問い合わせ

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F