
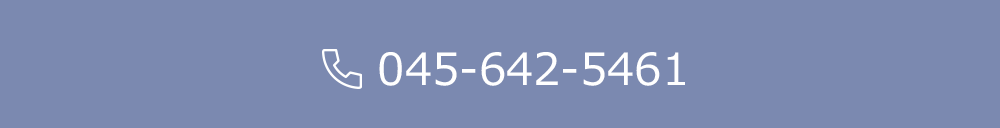

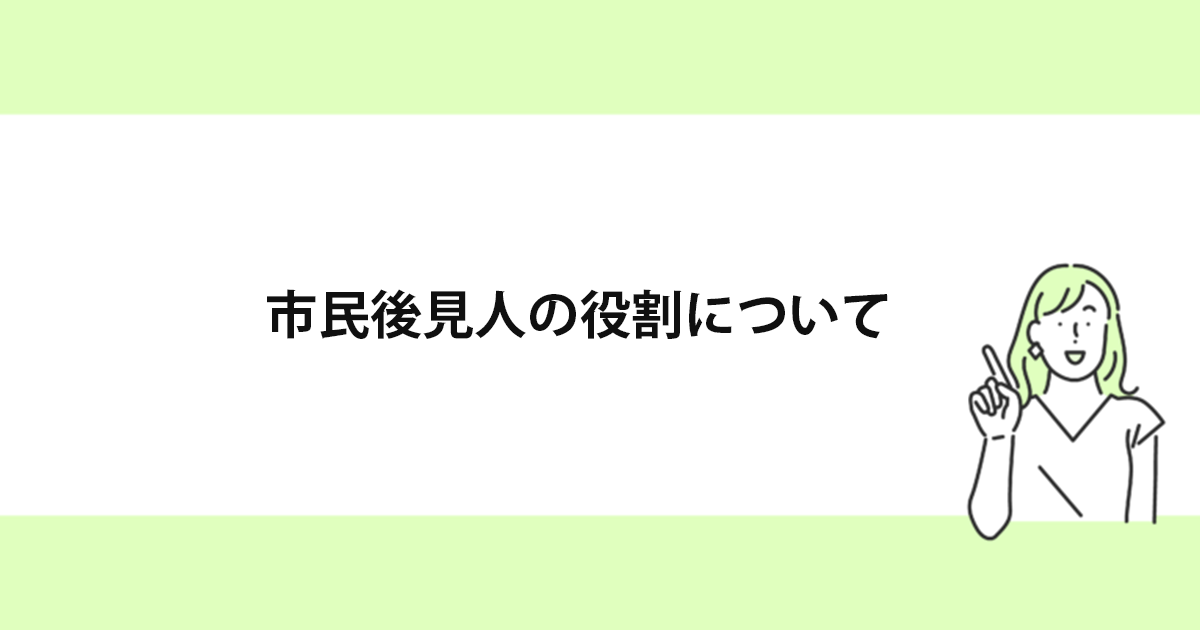
後見人制度では、一般的に被後見人の親族が後見人を務めることが多いです。
また弁護士や司法書士、社会福祉士などが後見人になることもありますが、中には市民後見人が務めるケースもあります。
今回は、市民後見人の概要や役割、どうすればなれるのかなどについて解説します。
市民後見人は、市区町村などが実施する養成研修を修了し、後見人精度に関する知識と態度を身に付けた一般市民の中から後見人に選任された人物です。
こちらを選任するのは、家庭裁判所の役割です。
市民後見人はあくまで一般市民であり、弁護士や司法書士といった専門職ではないという点が特徴です。
高齢化に伴う後見人制度利用者の増加に対応するため、地域全体が一体となって被後見人をさせる仕組みとして、こちらの活用が期待されています。
市民後見人は専門職とは異なり、生活者の視点を活かしつつ、被後見人本人の希望や意思を尊重したきめ細やかなサポートを行います。
また被後見人の預貯金の管理や日々の収支の確認など、本人の財産を守るための業務も行います。
さらに介護や福祉サービスの手続き、医療機関への受診同行など、本人がより良い生活を送れるように支援します。
ちなみに定期的に被後見人の元を訪問し、地域の中で孤立しないように見守り、関係機関との連携を図るのも大切な役割です。
前述の通り、基本的な役割は弁護士や司法書士などが後見人を務めるケースとそれほど変わりません。
一般市民から市民後見人になるには、まず市区町村や社会福祉協議会などが実施する養成講座に参加し、後見人制度の仕組みや後見人の職務内容などについて学びます。
また研修が修了したら、市民後見人として活動する意思を登録し、家庭裁判所から推薦されるのを待ちます。
その後家庭裁判所が個々の事案に応じて、登録された市民後見人の中から適任者を選任します。
つまり市民後見人になったからといって、必ずしもその本人の希望するタイミングで後見人として活動できるわけではないということです。
ちなみに市民後見人は、専門職と共同で後見人に選任されることもあります。
今後後見人制度の利用者が増えるにあたって、市民後見人が活躍するケースは増加することが見込まれます。
しかし市民後見人が担当できる事案が少ないことや、後見活動の責任が過大になること、活動支援者の業務負担が大きいことなど、まだ課題も多いです。
それでも、地域住民の視点を取り入れることで、より被後見人の生活支援が充実する制度であることは間違いありません。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。
お問い合わせ

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F