
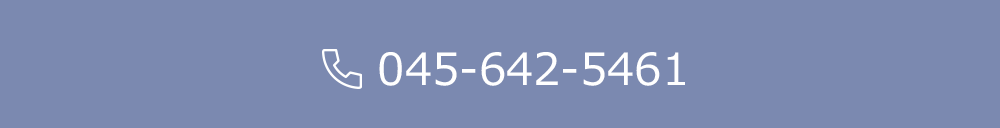

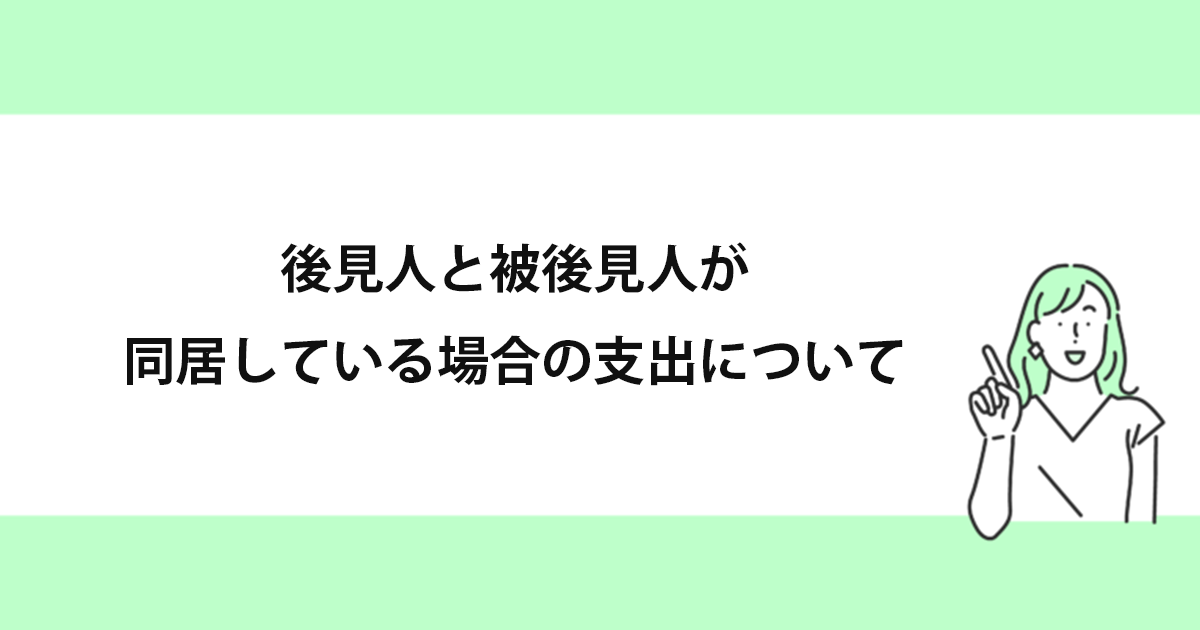
後見人制度は、判断能力が不十分な方を保護し、財産管理や契約といった法律行為を支援するための制度です。
また支援する側である後見人、支援される側である被後見人は、必ずしも別居しているとは限りません。
今回は、後見人と被後見人が同居している場合の支出の扱いについて解説します。
後見人と被後見人が一緒に住んでいるということは、被後見人の生活費=後見人の生活費という考え方もできます。
しかし、原則として同居している場合でも、支出は本人のためのものに限られます。
具体的には、後見人は自身の生活費を自身の財産から支払い、被後見人の生活費を被後見人の財産から支払います。
ただし後見人は、被後見人に扶養義務のある配偶者や未成年の生活費を、被後見人本人の財産から支出する義務があります。
つまり後見人と被後見人の生活費の支出はイコールにできないものの、被後見人とその家族の生活費は同じ扱いになるということです。
後見人が被後見人の扶養家族における生活費を支払うのは認められますが、こちらはあくまで被後見人本人の財産が十分にあることが前提です。
具体的には、支出によって本人の生活に支障が出ない範囲に限定されます。
そのため、扶養の限度を超えた高額な支出は認められません。
例えば扶養義務のない成人の子の高額な教育費、後見人の自宅改築費用などについては、本人の財産から支出できない可能性が高いです。
どのような支出が適切なのか判断に迷う場合は、事前に家庭裁判所に相談するのがもっとも確実な方法です。
後見人が選任されると、被後見人の財産管理は厳格に行われます。
そのため、以前は本人名義の口座から家族の生活費を自由に支出していた場合でも、後見人選任後はその限りではなくなります。
つまり、後見人の選任は被後見人だけでなく、その家族などの支出にも影響を与えるということです。
ちなみに、後見人が被後見人の家族の生活費を支払うのが認められているのは、贈与ではなく本人の扶養義務や婚姻費用の履行として正当なものとされるからです。
初めて後見人制度を利用する場合、細かいルールに混乱することもあるかと思います。
また後見人と被後見人の関係や、被後見人の家族構成などにより、遵守すべきルールは変わってきます。
もしどうすれば良いかわからなくなった場合は、自己判断せず家庭裁判所や弁護士、司法書士や社会福祉士といった専門家に相談し、具体的な指示を仰ぎましょう。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。
お問い合わせ

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F