
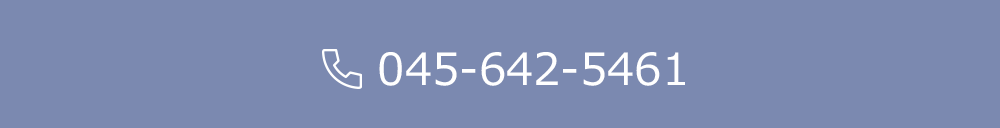

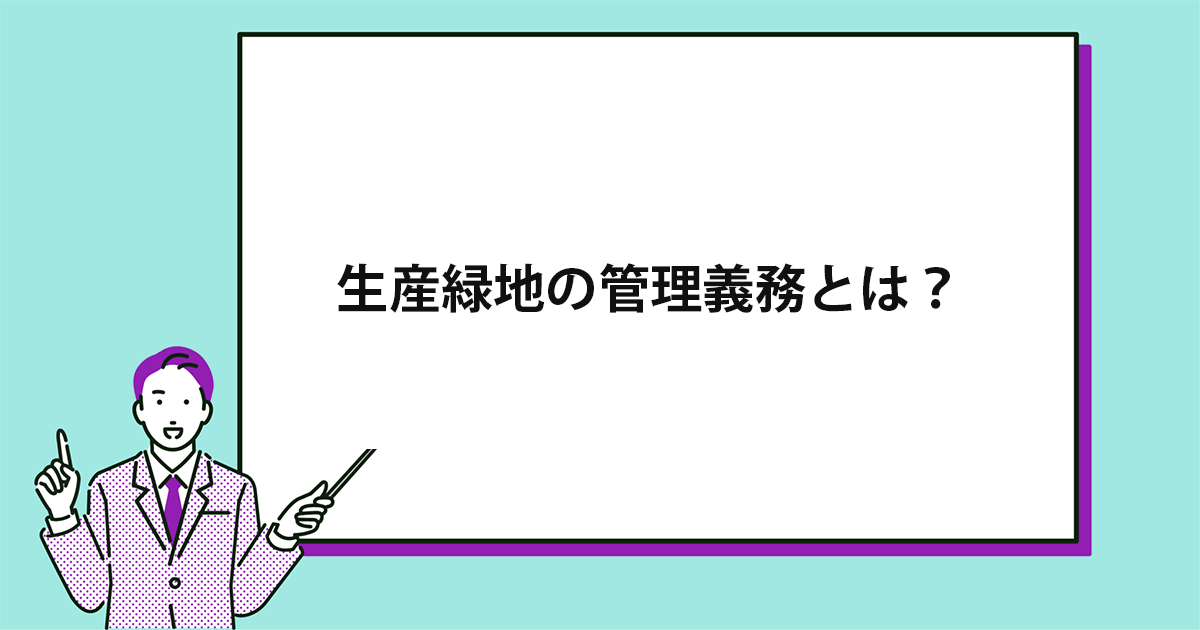
生産緑地は非常に特殊な土地であり、所有する方には管理義務が発生します。
これはもちろん、相続などで生産緑地を引き継ぐことになった方にも言えることです。
では生産緑地の管理義務とは、具体的にどういったことを指すのでしょうか?
今回は管理義務の内容を中心に解説します。
生産緑地の管理義務とは、具体的には農地としての維持、そして建築等の制限を指しています。
生産緑地では、原則として農作物等の生産活動を行う農地として管理する必要があります。
土地が荒廃しないよう、休耕する場合でも適正な管理が求められます。
また生産緑地内では、原則として建築物の新築や宅地の造成、土地の形質変更などの行為が制限されます。
こちらのルールを守ることも、生産緑地の管理義務と言えます。
ただし農業を営むために必要な農産物直売所、農作業用の休憩施設、資材保管庫などについては、市長村長の許可を得て設置可能です。
ちなみに生産緑地については、一定の要件を満たすことで、農地として他者に貸し付けることができ、こちらも管理とみなされます。
生産緑地の管理義務における根拠は、生産緑地法第7条に定められています。
この法律に基づき、生産緑地について使用または収益をする権利を有する者は、当該生産緑地を農地等として管理しなければならないとされています。
また生産緑地に指定されると、原則として30年間または所有者が亡くなるまで、前述した管理義務が継続します。
ちなみに所有者の意向により、特定生産緑地に指定されると、管理義務の期間が10年延長されます。
こちらは、その後も10年ごとの延長が可能です。
生産緑地の管理義務を怠った場合、所有者は生産緑地法第19条に基づき、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される場合があります。
また生産緑地の指定が解除されると、それまで受けていた固定資産税の軽減や相続税の納税猶予といった税制上の優遇措置が受けられなくなります。
固定資産税は宅地並みの課税に戻り、相続税の納税猶予を受けていた場合は、猶予されていた税金と利子を支払う必要があります。
生産緑地を所有する方は、税制優遇を受ける代わりに、都市計画における緑地機能の保全という目的を果たすため、責任を持って農地を管理することが求められます。
また生産緑地を相続する可能性がある方は、前もってこれらの知識を持っておかないと、実際相続したときにパニックに陥る可能性があります。
もちろん、生産緑地は条件をクリアすれば売却できる可能性もあります。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。
お問い合わせ

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F