
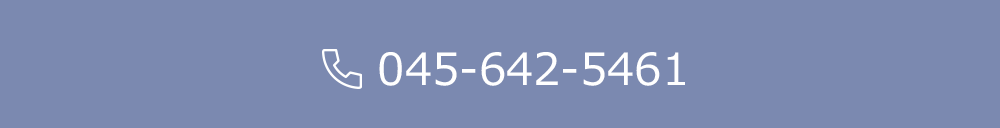

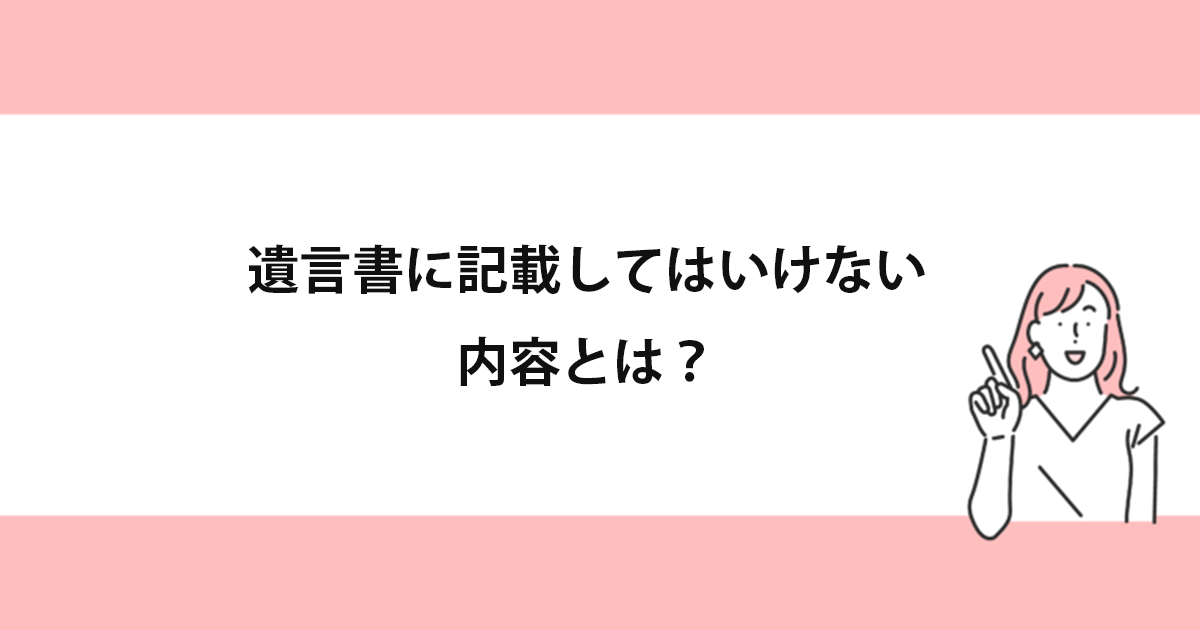
被相続人が預貯金や不動産について、残された家族に対し相続分や分割方法を指定したり、遺贈を行ったりできるのが遺言書です。
また自筆証書遺言の場合、使用する筆記用具や用紙などは基本的に自由ですが、記載してはいけない内容というものがいくつかあります。
今回はこちらの内容について解説します。
遺言書には、付言事項という項目があります。
こちらは残された家族などに宛てたメッセージなどを記載するものであり、法的効力は発生しません。
また付言事項には、感謝の気持ちなどを記載するケースが多いですが、逆に特定の相続人に対するネガティブな意見は記載しないようにしましょう。
例えば、生前面倒を見てくれた相続人Aと、面倒を見てくれなかった相続人Bがいるとします。
このとき「Bは面倒を見てくれなかった」と記載するのではなく、「Aは面倒を見てくれた」と書き換えるのがポイントです。
遺言書に記載するのは、あくまで遺言書によって指定できる内容に限ります。
例えば養子縁組や結婚、離婚といった身分行為における指定は、当事者双方の意思が必要であるため、遺言書で指定することはできません。
ただし、子どもの認知については遺言書での指定が可能です。
また臓器提供や葬儀方法など、亡くなった後のことについて指定することにも、法的効力は発生しません。
こちらはあくまで付言事項として、相続人に被相続人の希望を伝えるものになります。
つまり、相続人がそれに従わなかったとしても、特に問題はないということです。
公序良俗に反する内容も、遺言書に記載してはいけません。
公序良俗とは、簡単にいうと社会のルールや常識のことをいいます。
例えば正式な配偶者や子どもがいるにもかかわらず、不倫相手にすべての財産を遺言させる内容を記載した場合などは、公序良俗違反に該当する可能性があります。
またある人物に財産を相続させる代わりに、特定の犯罪行為を行うよう指示するような内容も、完全な公序良俗違反です。
公序良俗違反に当たる遺言書については、無効となることが民法90条で定められています。
遺言書を作成しようとする被相続人は、まず遺言書のルールについて理解することをおすすめします。
必要事項や禁止事項は多岐にわたりますが、1つずつポイントを押さえながら作成していけば、法的に不備のない遺言書が完成する可能性が高いです。
もし自身の力だけで作成するのが不安なのであれば、弁護士や司法書士、行政書士などに相談してみてください。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。
お問い合わせ

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F